このジュエリーと同じものを別のお店で売っているのを見たけど、あっちの方が安かったわ。どうして?
(え?一緒のものなのに値段が違うことがあるの?)
所詮「ジュエリーの値段はあってないようなもの」だものね。
そんなこと言われても…
ジュエリーを販売しているときに「宝石やジュエリーの値段はあってないようなもの」と言われたことはありませんか?
確かに同じ商品でもお店によって価格が違うことがあります。
さらに言えば、見た目はよく似ていても価格が全く違う商品が同じお店に並んでいることもあります。
そのため、いろんなお店に通うお客様の中には
「ジュエリーは同じものでもお店によって好きなように値段をつけている。」
と思っている方もいらっしゃるようです。
結論から言うとそんなことはないのですが、どうして値段が違うのかきっちり説明できる販売員さんも少ないのかもしれませんね。
私自身、新入社員の時にお客様からこんなことを言われていたら上手く説明できなかったかもしれません。
今回は同じようなジュエリーでも値段が違うのがなぜなのかを2つのポイントから解説します。
なぜジュエリーの価格が違ってくるのでしょうか
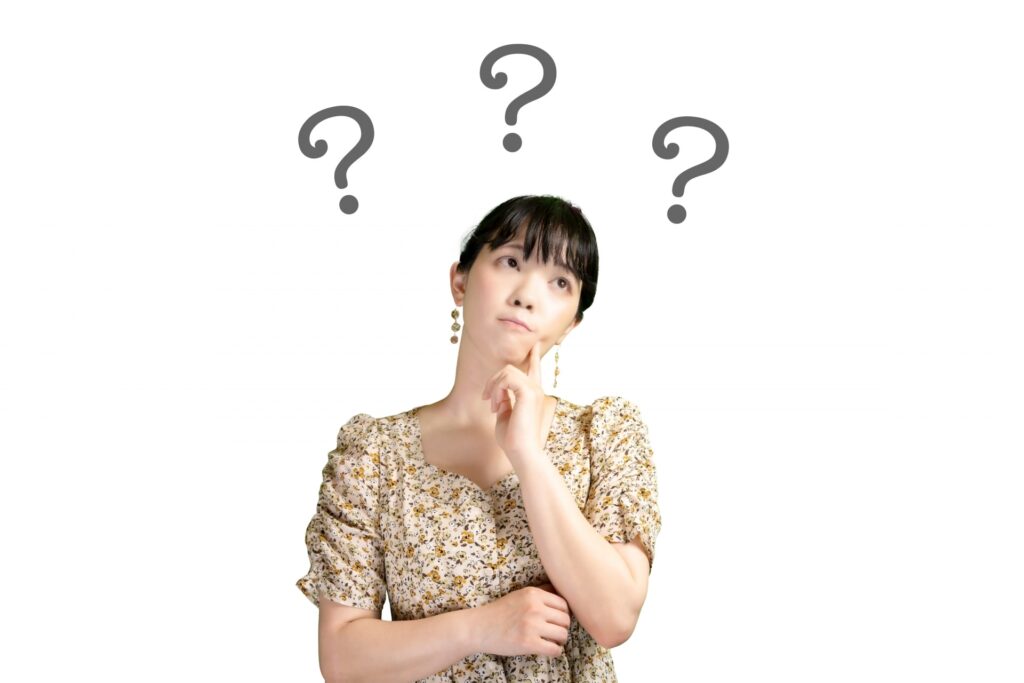
ジュエリーの価格が変動する理由は沢山ありますが、大きく分けてこの二つに分けられると思います。
- 通ってきた業者の数
- 素材の価格変動
まずはジュエリーの値段の付け方、そして業者の数が増えるとどんなふうに価格が変化するか見ていきましょう。
ジュエリーの値段の付け方
まずは宝石の価格がどのように付けられているか知りましょう。
①素材代(宝石・地金)
+
②工賃
+
③卸業者の利益
+
④小売店の利益
=お客様の購入金額
お客様への価格は①素材代に②〜④の利益が上乗せされている
ジュエリーはお客様の手に届くまでに、たくさんの人の手を渡ってやってきます。
まずは①素材代、それをジュエリーに加工する②工賃がかかります。
さらに③卸業者を通って④小売店へと段階を踏んでお客様のもとへ行きます。
もちろん、業者を通るたびにそれぞれの会社が利益を上乗せしていきますから、お客様が購入する金額はその分も踏まえた価格となります。
例えば①素材代を5万円、そこに②工賃〜④小売店までそれぞれ1.5倍の利益を乗せていくとどうなるでしょうか。
①原価(宝石・地金) ¥50,000ー
②工賃 50,000×1.5=¥75,000ー
③卸業者 75,000×1.5=¥112,500ー
④小売店 112,500×1.5=¥168,750ー
原価50,000円をお客様に¥168,750ーで販売する
原価5万円のものがお客様の手に渡る頃にはこんなふうに中間マージンが積み重なっていることがわかります。
今回はわかりやすく1.5倍で計算しましたが、業者によって掛け率は変わりますから、あくまで例としてみてくださいね。
通った業者の数によって、さらに値段が高くなることも・・・

ジュエリーが通ってきた業者の数によって価格が変動するとお伝えしましたが、実際にどれぐらい変化するものなのでしょうか。
宝石は天然のものです。
珍しい宝石やなかなか手に入らないものは、いろんな卸業者に声をかけて探す場合もあります。
ものによっては卸業者の間でジュエリーを貸し借りする場合もあり、そうなると通した業者の数だけ中間マージンが発生するので価格が高くなっていきます。
もし先ほどと同じ①原価¥50,000ーの宝石を③卸業者を3つ通して販売した場合、どれぐらい価格が変わるのでしょうか。
同じようにそれぞれ利益を1.5倍で計算していきます。
①原価(宝石・地金) ¥50,000ー
②工賃 50,000×1.5=¥75,000ー
③卸業者 75,000×1.5=¥112,500ー
③卸業者 112,500×1.5=¥168,750ー
③卸業者 168,750×1.5=¥253,125ー
④小売店 253,125×1.5=¥378,687ー
原価50,000円をお客様に378,687円で販売する
どうですか?
卸業者を2カ所増やしただけで、最初に計算した価格よりも2倍以上に跳ね上がりました。
ここからわかる通り、そのお店がどれぐらい中間業者を通しているかでジュエリーの価格は大きく変動します。
ですから同じ製品であってもA店とB店では違う値段で販売していることがあるんですね。
それが「ジュエリーの値段はあってないようなもの」の正体なんです。
もちろん工賃や会社の利益率などはそれぞれ違ってきますから、その分さらに価格に幅が出ますね。
素材の価格変動による値段差

他にもジュエリーの価格が変動する理由はいろいろあります。
①新しい産地が見つかって宝石の価格が下がる
宝石の価値を決める重要な要素の一つである希少性。
希少性が高い宝石はそれだけ価値が高く、販売価格も高くなる傾向があります。
ですが稀に新しい産地から大量に見つかり、それによって希少性が下がり価格が下がってしまう、なんてことも。
希少性が下がっても、いろんな人に認知されたおかげで逆に需要が高まることもあるので一概には言えませんが、大量に採掘されることで価格が変動するのは割とあります。
②何らかの理由で宝石の供給量が減ってしまう
こちらは先ほどとは逆のパターンです。
鉱山が閉山したり、産出量自体が減ってしまい宝石の供給量が少なくなるとプレミアがつき、必然的にその宝石の価格が上がりやすくなります。
有名なところだとパライバトルマリン、アレキサンドライト、パパラチアサファイアあたりですね。
また、現在ダイヤモンドはロシア・ウクライナ問題など社会情勢的な理由から価格が上がっています。
③需要が急激に高まり、供給量が追いつかない
ある宝石が大ブームになって供給量が追いつかないと、品不足から価格が高騰する場合があります。
一時期中国で珊瑚の大ブームがあり、それによって日本で珊瑚が手に入りにくくなったことがありました。
現在は真珠ブームで、日本の真珠が山のように買われていますよ。
ここ数年、新種ウイルスの影響でアコヤ貝の稚貝が大量死してしまったため、さらに価格が上がっています。
④金・プラチナの高騰・急落
宝石だけでなく、ジュエリーの素材としてよく使われている金・プラチナも価格に影響します。
金・プラチナの価格は株価のように日々変動していてネットでもすぐ検索ができますよ。
使う素材の価格が変わるため、出来上がったジュエリーの価格も変動しています。
ここ最近、金の価格が一万円を超えた!と話題になりましたね。
現在は金の価格が高騰しそれとともにプラチナの価格も上がっていますから、以前よりも素材代が高くなってしまっているんですよ。
⑤為替による価格の変動
宝石、金、プラチナなどの素材の多くは海外から輸入したもの。
そのため為替によって価格が変動してしまうことがあります。
最近は円安のため海外ブランドが軒並み価格改定をおこなっていました。
ブランドによってはこれからも価格改定で値上がりする可能性があるそうですよ。
ジュエリーの価格はいろんな要素で成り立っている

「宝石・ジュエリーの値段はあってないようなもの」
そんな風に言われてしまうのは、同じような商品でも店によって価格差があるためです。
これは通している業者の数、素材代、為替などさまざまな要素が組み合わさり起こります。
同じ見た目の商品でも仕入れた時期によって価格が違うのは本来ジュエリーであれば当たり前に起こる現象なのですね。
ですが、販売スタッフにはそういった事情が伝わっていないことが多く、詳しいお客様に質問されると困ってしまうことがあるようです。
お客様もそれを見てお店に不信感を持ってしまうこともあります。
ジュエリーは高額なお買い物ですから、お客様からの質問にはスムーズに自信を持ってお伝えしたいところですね。
お店の中で商品の価格帯に違和感があるものはありませんか?
「どうしてこの商品とこの商品では値段が違うのか」という疑問はお客様に聞かれる前に確認しておいた方が良さそうですね。











